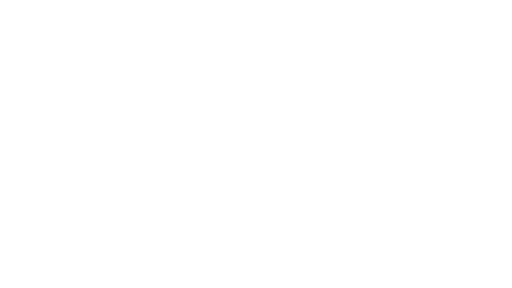クラブ創設25周年シャツ配布決定! 北村直登さんインタビュー「大分トリニータは骨太なクラブの象徴でもある」
クラブ創設25周年シャツ配布決定! 北村直登さんインタビュー「大分トリニータは骨太なクラブの象徴でもある」

8月17日、明治安田生命J1第23節・鹿島アントラーズ戦で配布されるクラブ創設25周年シャツのデザインを手がけてくれた、大分市在住の画家・北村直登さん。独特の世界観を盛り込んだ両面が前面のシャツは、ポップでカラフルで魅力的だ。
かつては自らがサッカープレーヤーでもあった北村さんがそのデザインに込めた思い、大分に住み着いた理由や、絵画とサッカーとの関わり合いについてじっくりと話を聞くうちに、サッカーで積み重ねたものの大きさが見えてきた。
積み重ねることが楽しかったサッカー少年時代
——北村さんご自身も、サッカープレーヤーだったんですよね。
記憶をたどると幼少期はサッカーしかやってなくて、サッカーのことしか考えてなかったんです。大学生までそんな感じでいたんですけど、あるときふと、もしもプロサッカー選手になれたとして、それ以降のことを想像したときに恐怖を感じたんです。
高校生くらいまでは考えがボヤッとした中にいたんですね。プロになるしかないと思っていたから、ならない場合の想定も出来ていなかった。でも、大学生になると、プロになれなかった人とか、なったけどすぐに怪我で辞める人とかいった情報がわっと入ってくるようになって、自分もそれくらい危うい存在だなと気づいた。このままサッカーを続けて、もしも運良くプロになれたとしても、30歳超えるまでプロでいられるのはすごくいい選手で、それはひと握りだけなんです。それに気づいたときに、そのハードルの高さを考えて。そこに懸けるだけの力が自分に本当にあるのかと思ったら、足がちょっとすくんでしまったんです。
——それで、絵の世界に転向を。
すぐにぱっと行けたわけではないんですけど。サッカーをやっているときに何が楽しかったか、何を魅力的に思っていたかを考えると、積み重ねることがすごく楽しかったんです。だからスポーツ選手としてではなくても、年齢的な限界のないものに対して積み重ねていきたいな、死ぬまでやれることがいいなと。
それと、サッカーは言語を超えた交流が出来るでしょ。ブラジル留学も、言葉を覚える前に行って、ブラジルの人たちとの関係を築いた。同様に言葉を使わなくていい職業として、いろいろ挑戦した中で、「もしかしたら上手くいくかも」と思えたのが絵だったんです。
——いつごろから描きはじめたんですか。
サッカーを辞めてしばらく経ってからですね。子供の頃から図工と体育だけが生き甲斐みたいな感じでした。ものを作るのも好きだし、高校生の頃から勝手に家具を塗ったりしてましたね。
すべてサッカーに置き換えて考えていた
——絵描きだって、安定した生活が送れる職業ではないと思うんですけど。
絵画における都合の悪いことは、すべてサッカーに置き換えて考えてたんです。サッカーには勝ち負けがあったり、なんなら監督に気に入られるか気に入られないかというところでも、すでに運が関係していたりもする。でも絵は、自分が負けたと思わなければ負けはないわけで、試合とは違って時間が決められているわけでもない。勝ち方にもいろいろあったりして、「負けない立ち回り」が出来た。そういう意味ではサッカーとは全然違ってました。
逆に、サッカー式に考えたほうがいい面もあります。スランプというものが絵描きにもあるらしいんですけど、サッカーで「ちょっと今日、上手くボール蹴れんわー」みたいなことは、試合中には言わないでしょ。そもそもそんな発想にもならないし。だから絵を描くときも「描けない…いや、描けるやろ」って、とにかく走り続ける。負けるときも負け方があるという感じで。
スランプっぽいものがあったとしても、そういう認識では捉えてなくて、訓練というか。描いていて線がボヨボヨしてる日とかもあって、なんだか思ったとおりに描けないんだけど、「今日はまあ、ボヨボヨしている線を描く日だな」と考えるんです。
絵を描いていて陥りがちなのは、いちばんいいときの自分を追い求めていくこと。尖らせて、最高MAXの部分を目指し、前よりもいい作品をという思考回路になりやすい。でも、そういうときはサッカー的に、いちばん調子の悪いときの底上げをしていくようにするんです。「ボヨボヨしてるときにもこういう絵は描けるし、こういう仕上がりができるんだ」ということを探していったりね。
——まさに毎日トレーニングしている人の思考ですね。
そうそう。だから調子の悪いときの戦い方をちゃんと準備しておく。サッカーが嫌になったらよくないでしょ。同じように絵に対しても、何が楽しいとかを考えておくんです。
——ほかのアーティストさんと比べて安定感がある(笑)。
だから機微という部分ではあまりないのかもしれない(笑)。作家としての情熱とか魂とかっていう意味では、かなり太いというか。そういうタイプじゃないし、それは向いてないと思うんです。画家になるための弱点を、体育会系のノリで補填していくという感じです。
やっぱり描いた量は嘘はつかない
——道端で絵を売っていた時期を乗り越えて、その後は右肩上がりですね。
おかげさまで本当に運がよくて。何回も奇跡と思えるようなことが、自分の中でありました。でも実際には、はじめた頃といまと、何も変わってないんです。最初に決めたルールをずっと守ってて。たとえば、毎日描くとか。絵が売れなかった次の日は休んじゃいけないとか。上手くいかなかったときは休んじゃいけなくて、上手くいった日は休んでいいけどそういうときは休みたくない、みたいな。とにかく描き続けるルールを守ってきました。
——ものすごくトレーニング的ですね。
はい。絵を描きはじめるのが遅かったので、もしもほかの作家さんと比べられたときに、やっぱり描いた量は嘘はつかないので、いまもそこだけしか意識してない。だから一枚でも描くための状況をどうやって作っていくかを、当時から考えてるんです。
いつかは必要とされなくなるときが来る。売れなくなったら描くことをやめなきゃいけない。それが自分の中のルールなんですね。自分の中で「社会の役に立たなくなったときに、それはもう画家とは呼べない」という設定にしてある。だから、そういう空気を感じた催事の後なんかはすごく焦ります。
いまは僕が想像していたよりもはるかに高いところにいるんだけど、自分の力ではここに立っていなくて、いろんなハシゴをかけてもらって、作品を売りやすいところにいるけど、そのハシゴは全部外されるという前提に、自分の設定ではしてあるんです。
自分で浮力を持っているわけではないから、グライダーのようにしながらなるべく遠くまで飛んでいけるようにという努力はするけど、それ以上は多分、僕の力では飛べなくて、いつかは落ちる。それを前提に、出来るだけ遠くまでと。
——自分は淡々と描き続けてきたら、周りの人たちが上げてくれた。
そうなんです。周りの人が「上げてあげる」って言ってくれただけなんです。いまも以前も上げてもらったから、僕にはより遠くに飛ぶ義務がある。一度作品を売った以上、自分の匙加減で落ちたりするのは許されないんです。
——売れなきゃいけないというプレッシャーはないんですか。
売れる絵を描こうとすると売れなくなるんです。特に序盤なんて、上手くいったときを真似て「これが売れる絵だ」と思われるものを大量に描く。すると次の催事で売れなくなる。そういうことを何度も繰り返してきました。
結局、描いているものが真実か真実でないかを、人には結構見分ける能力があるんです。それで、僕にとっては下手な絵だったり、いろんな作風に挑戦した中に、その人が好きだと思えるものがひとつポンとあるから、買いたいと思ってもらってるのかなと思うようになって。それからは何も考えてないです。描くのが楽しかったり、描きたいと思ったものを描いたりで、売れる・売れないということはあまり意識してない。ただ、ニーズとしてこの絵のニーズが多いというのはもうある程度は理解しているから、それは催事のために準備するという感じです。売るために描くというよりは、そういう正しい姿勢で向き合っておくということしかやってないです。
大分の人はみんな人のことをあたたかい目で見る
——意外とみんな知らないと思うけど、大分生まれじゃないんですよね。
そうなんです、生まれは福岡で、高校時代に流れ着くように大分に来ちゃったんです。僕はまったくホームシックにならないタイプで、ブラジル留学後の復学先が大分県の学校だと言われたときも「ふーん」という感じで。
留学中も、周りの友達はホームシックにかかって「帰りたい」と泣いてたりしたんですけど、僕は一切、家に連絡を入れなかったんですよ。3ヶ月以上経ってから親のほうから「手紙くらい書きなさい」という手紙が届いたくらいで。その頃、初めて写真を撮るようになって、その写真を入れて手紙を送るようにしたんです。
そんな感じなので、住むところについてはあまり意識しなかったですね。
——そのまま大分に居ついてしまった。
はい。福岡と大分の違いを感じるようになるのはそれよりずっと後のことなんですけど。大分の人ってみんな優しいんですよ。福岡の人ってみんな自分の話をして気が済んで終わる、みたいなことが結構あって。相手が聞いてなくても喋るし(笑)。大分の人とはちょっと違う空気感がある。
学校でも「あれ、大分の男の子はすごくおとなしいな」と感じていて。福岡の子たちは日常的に罵ったりもあったし、相手の欠点も「それはお前が悪いっちゃん」という感じでズバリと指摘する。それにやられたりやったりを繰り返していた中学生時代とは違って、大分では人のことをあたたかい目で見て、かける言葉も優しいということに、次第に気づいていったんです。絵を描きはじめて、大分のことを発信したいと思ったときに、強く感じたんですよね。
大分の人は、僕が福岡式にわーっと話しても、きちんと話を聞いてくれるんですね。「あ、こういうふうに人の話を聞くと、相手を気持ちよく出来るんだな」ということを、大分の人に教えてもらいました。絵をはじめたばかりの苦しいときにもいろんな人に支えてもらって。福岡だったら多分、潰れていたと思います。
トリニータは見ているだけでドラマがあるクラブ
——大分トリニータ創設25周年記念シャツのデザインはどういうところから。
サッカーに携わっていながら、トリニータの応援にはあまり行けてなかったんです。ただ、行かないなりに、行かない人たちはどうやったら興味を持つんだろうといろいろ考えていて。カラフルな、いつもの青と黄色じゃないパターンもちょっとやってみたいなという提案もしながら、やっぱりトリニータを好きになるには、同じ色を着てみんなで応援することの意味というのもあるし、と。そこらへんを上手く落とし込みました。
——あのデザインの意図は。
25周年の中でこんなに紆余曲折あるクラブも珍しくて(笑)。J1で戦ったり、J3に落ちてもまたJ1に戻ってきたりと、ポテンシャルの高さを示してもらえているのがすごくうれしいんです。骨太なクラブの象徴でもある。そういうのをサポーターのみなさんは知っているし、大分に住んでいながらトリニータのことをあまり知らない人たちも、過去を面白くたどったり、これからの未来に一緒に興味を持ってもらったり出来たらいいなあと。見ているだけでドラマがあるクラブだから。
みんなが興味を持って応援してくれることが第一ですからね。「あのシャツ欲しい」という声が届くと、そう思ってもらえるものを作れてよかったなと思っています。
——限定2万5000枚。
ねえ。なくなるくらい人が来てくれたら、僕としてもすごくうれしいです。また次の機会、次は僕じゃなくても、またクラブがそうやってプレゼント企画を出したらみなさんが反応してくれるといういい関係が続いていくといいですよね。
トリニータがビッグクラブになるとき、大分もいい都市になっている
——画家・北村直登として見た大分トリニータは。
実は、スクールコーチのアルバイトをしていた時期があるんです。当時のトリニータは経営難で、社員のみなさんがしんどい思いでやっていた時期のことです。それを目の当たりにしてきたんですよね。
だから、大分そのものが潤ってもらいたい。僕が納税を大分に決めているのも、福岡のような潤っている都市に行くより、大分の観光資源になれたりとか、そういう面でもしも僕が力になれるのだったら、それを目指したいなと思ったからです。
トリニータが疲弊しているということは、大分も疲弊している。トリニータがもしビッグクラブになるんだったらそのときは大分もすごくいい都市になっているはずだから、発展してもらいたい。ただただそれだけです。
僕は今回こうして関われたからすごく幸せですけど、関われなくても、トリニータ、ひいては大分全体にプラスになるように、これからも働きかけていきたいと思っています。
8月17日(土)明治安田生命J1リーグ第23節 鹿島アントラーズ戦にて先着25,000名様に25周年記念シャツを配布!
明治安田J1第23節・鹿島アントラーズ戦において、クラブ創設25周年を記念し、北村直登氏デザイン記念シャツが先着25,000名様に配布されます!
詳細はこちら

北村直登さんプロフィール
1979年、福岡県春日市に生まれ、幼少期よりサッカー漬けの日々を送る。1995年にブラジルへ1年間のサッカー留学。その後、大分県の高校へ復学し、以来、大分在住となる。大学卒業後にフリーター生活を送る中で、2002年に絵を描きはじめ、路上で自作の絵を売ってなんとか食いつなぐ日々を超えて、グループ展やワークショップ、イベントなどに参加し、個展も開催。次第に東京・伊勢丹をはじめ全国での催事を通じて知名度が上がり、フジテレビドラマ「昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜」への作品提供で一気にブレイクした。
現在も大分市にアトリエを構え、精力的に制作に励んでいる。
Official HP:https://naoto-kitamura.tumblr.com/
今後のスケジュール
7/10~7/23 伊勢丹新宿店本館2Fにて「POP UP SHOP」
7/25~7/30 大分銀行宗麟館にて作品展示
8/3 cafe GARDENにて「親子DEワークショップ」
8/7~8/13 北九州市・井筒屋小倉店新館1階アトリエ ワークスにて「画家・北村直登展」
8/8~8/20 大分市・トキハ本店にて「北村直登アートギャラリー」
(インタビュー・構成・執筆:ひぐらしひなつ)